初めての中国(その1)今年(2004年)4月、杭州、蘇州、上海 を旅行しました。私にとってはかなり刺激的な 旅だったので、雑感を記してみます。中国通の 方にとっては、何をいまさらという内容かも知 れないし、私の理解が不適切なことがあるかも 知れません。ご指摘いただければ幸いです。 1.自動車事情: 杭州、蘇州、上海の三都市間の移動と観光地巡りは貸切の小型バスだった。 都市の中心部では渋滞もあったが、高速道路で結ばれている都市間はスムーズ に移動できた。高速道路を走る車の数は日本の東名・名神と同じ程度だった。 高速道路を走りながら気がついたこと。それは農村地帯の民家のまわりに駐車 している車が全く見当たらないことである。一般道路を走っている車も見当た らなかった。ということは、自家用車は一般家庭にはまだほとんど普及してい ないということであろう。もうひとつ、日本の高速道路との違いのひとつは、 車間距離である。時速80キロ程度と思われるときの車間距離が10メートル 位というのもざらである。日本では「このアホめ!」と叫びたくなるような割 り込みをしてくる車も多い。日本の高速道路に設けられている車間距離の確認 標識は見当たらない。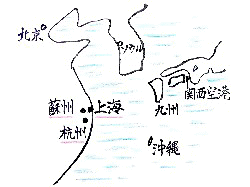
市街地での交通風景(杭州) 市街地での道路横断は恐怖である。青信号で横断歩道を渡るときでも右折車 が容赦なく突っ込んでくる。中国では車は右側通行なので、右折車に優先権が ある。その優先権は車同士だけでなく、歩行者に対してもあるようである。 いや、右折車だけでなく、全ての自動車が歩行者に優先するようである。市街 地でタクシーに乗ってみるとスリルがある。車一台分位の車間距離でスピード を出し、少しでも車間距離に余裕ができればすかさず右に左にと割り込む。 クラクションをひっきりなしに鳴らし、急ブレーキ、急な進路変更はざらであ る。このような環境で生き抜くにはかなりの技量が必要である。私の見た限り では、タクシーの運転手は全て中年以下の男性だった。自家用車と思われる車 を運転している人でも、女性は見かけなかった。そうだ、ここでは車の運転は プロの仕事なのだ。青葉マークを付けてよたよたと走るおばさんやネエチャン が幅を利かせる世界ではないのだ...。と考えているうちにひとつの記憶が 蘇ってきた。かつては日本でもそうだったのだ。「カミカゼタクシー」が世界 に勇名をとどろかせていたではないか。 (ちなみに、「カミカゼタクシー」の語は広辞苑にも載っている。) 2.積木工事: 現地ガイド曰く、現在中国で元気な産業の順位は次のとおりである。 1位:不動産 2位:電話 3位:自動車 4位:塾 5位:眼鏡 都市部では古い住宅が取り壊されて高層ビルが建てられている。古く朽ちた2 階建ての旧住宅街と道ひとつ隔てて高層ビルが立ち並んでいる。旧住宅街を歩 いてみると、路上のところどころに人が群がっている。4−5人が小さなテー ブルを囲み、その周りを見物人が取り囲んでいる。カードゲームに興じている のである。麻雀をしている人達もいる。中国の遊びといえば麻雀と思い込んで いたが、カードの方が多かったのに少し気落ちがした。なぜなら、今回友人と 4人でツアーに参加したのは、4人で中国の大きな麻雀牌を積む体験をしてみ よう、というのが大きな理由だったからである。
ゲームを楽しむ人々(上海) 最初にやった積木工事は杭州のホテルだった。嬉しいことに2階に数室の麻 雀部屋(個室)があった。使用料は1室50元(約650円)でお茶とサトウ キビがサービスとして出てきた。意外にも全自動の卓だった。牌は予想通り日 本よりも一回り大きかった。花牌はあったが赤牌はなかった。戸惑ったのは点 棒がなかったことである。中国でも常識のある人は賭けるだろうし、賭けたら 計算をし易くする工夫はするだろうに、どうしているのだろうか。こんなこと もあろうか、と我が4人組の組長は手を打っていた。点棒代わりに予め購入し ていたカード(トランプ)を使ったのである。この組長は、積木工事で土産物 代を稼ぎ出そうという魂胆が見え見えの悪役である。 二回目の作業は上海のホテルだった。このホテルも2階に数室の麻雀部屋が あり、夕食後に覗いてみると若い綺麗なお姉さん達が卓を囲んでいた。何とな く幸せな感じになったが、その日は疲れていたので翌日に期待することにした。 ところが、翌日フロントで申し込むと、中年の女性マネージャから「今日は麻 雀部屋は使えません」と意外な返事が返ってきた。「昨日は使えたじゃないか」 とか、「近くに雀荘はないか」などと食い下がったら、宿泊の部屋に道具を用 意することができるとのことだった。部屋で待っていると二人の若い娘が折り たたみ式のテーブルと牌を運びこんできた。テーブルは自動式ではなく、上に 毛布がかぶせてあるだけである。何はともあれご開帳となったが、牌を並べる 作業には一苦労した。最近は全自動に慣れてしまっていることに加え、テーブ ルの縁に突起がないので牌を並べにくかったことである。また、牌が大きく、 片手で押さえられるのは5枚だけ(日本では6枚)だったこともある。お茶も 何もサービスなしで使用料は100元だった。 3.俊子終焉の地: 上海で是非訪れてみたい場所があった。私の親戚筋(名前だけが)にあたる 作家 田村俊子 の亡くなった場所である。明治末期から大正にかけて人気作 家となった俊子は、晩年を上海で過ごした。日本租界のあった上海は、大陸に 自由を求め、心の束縛を嫌う日本人を惹きつけたのかも知れない。しかし、奔 放な俊子といえど単身中国で暮らすにつけては、深い孤独感に慟哭することも あったに違いない。俊子が倒れたのは終戦に近い1945年4月13日夜であ り、16日に亡くなった。場所は日本租界の一角で、現在の四川北路と昆山路 が交わるあたりということである。上海観光の3日目は自由行動の日であり、 上海の中心部に住んでいる友人宅に4人で押しかけた後、夜の雑技団見物まで 各自で散策することになった。我が4人組の飲兵衛3人が文学に興味を示すこ とは考えられないので、私は一人で出かけた。
俊子が倒れたあたりの昆山路(上海) タクシーで目的地の近くまで行き、ぶらぶらとあたりを眺めた。二つの通り が交差するあたりの一角では、古い住宅が壊されている途中だった。近くには 高層ビルが建っていたが、古い住宅地も残っていた。少しわき道に入ると、昔 ながらの商店街があった。幅6メートル近い道路の両脇には2階建ての古い建 物が連なり、野菜、魚、調味料、肉、肉饅頭、ラーメンなどを売る狭い間口の 店が並んでいた。通りは平日の午後にもかかわらず人通りが多く賑やかだった。 このような風景は、俊子が住んでいた時代と変わりがないのに違いない。俊子 も足を向けたであろうか。いや、ホテル住まいをしていた気位の高い俊子は、 このような場所を好んで歩くことはしなかったかも知れない。俊子が住んでい た北京路のホテル「北京大樓」のあった場所は、事前調査が不十分だったこと もあり、探し当てることができなかった。 私が歩いたのは、奇しくも俊子が倒れた4月13日だった。 (2004‐4‐29記 : つづく) 初めての中国(その2)へ エッセイメニューへ トップページへ